
白 夜
「日が沈まなくなったわ」
私は呟いて起き上がろうと腕を差し伸べた。しっかりした手が私の手を掴み、空気に乗せるように立ち上がらせてくれる。私はそのままその手を離して、窓辺に近づいた。夕焼けと朝焼けが溶け合って、高山が薔薇色に染まっていた。この北の大地に夜の無い季節がやってくる。
「彼女に会いにゆこうと思うの」
そう言って私は傍らに立つ者に微笑みかけた。柔らかな金の髪を持つ私の眷属。彼が一瞬複雑な顔を見せたのを、私は見逃さなかった。青い瞳が眷族にあるまじき、痛みと困惑に揺れる。この私を慕う、その心情を私が理解しないわけではない。けれどもより大きな理があり、定めがある。私たちは私たちの身体の奥に潜む定められた掟に従って行いを決めるもの。それに、どのみちそれは今すぐではない。
「仕度には時間がかかるもの」
そう言いながらもその翌日には、私は人間たちが踏み入れることを恐れる森の奥のさらに奥。聖なる森への道を辿った。私には確信があった。今はそれぞれの仮庵に住まいする私の姉妹も、こうして内なる声に従って聖なる道を辿っていると。
聖なる森の前に来ると、私の姉妹が私を待っているのが見えた。同じ黒髪、同じ顔立ち。私の双生児の姉妹。彼女はそっと私の名を呼んだ。
わずかに瞼を伏せた彼女は、とても静かに私を待った。光が彼女の睫毛に溜まり、虹を作っている。彼女の瞳は私と異なり青い。双生児の私たちはそっくりの顔をしているだろうに、時々彼女の慎ましやかな横顔を私は羨ましく思うのだ。
「私達の時期が近づいているのが、わかる?」
私は彼女を見つめながら言った。思ったとおり、彼女は柔らかく微笑みながらうなずいた。その優しい瞳の色が私はいつでも好きだった。
「私達二人の時期」
本能の奥に潜む約束。ほんの少しの寂寞は温かさの裏返し。
「では私は貴女の眷属を」
「私には貴女の眷属を」
取り交わす定句は誓いの言葉のよう。私たちはしっかりと抱き合って、互いを祝福し合った。一族の繁殖の時期に差し掛かり、私たちは準備を始める。一族の女王の間でのみ行われる秘儀。神秘と矛盾に満ちたこの一連の儀式に、私は本能の不思議を感じる。私のものは貴女のもの。貴女のものは私のもの。私は私の眷属の、金色の髪を思い起こした。儀式の後、もしも彼女が生き残っていたら、と考えてから、それ以上の思索は無意味と位置づける。きっと彼女も自分の眷属の事を思い浮かべているのだろう。私たちは双生児。片時も離れずに生きてきたのだから。この瞳の色のように反しながら、常に重なり合って響きあう。想いも思考も共鳴しながら。
寂しいのは自分の眷属を想っての事なのかもしれない。私たちの種族は純粋な男性体を産まない。人間の中から自分たちの嗜好に合わせた者を選び出し、仲間に加える。純血は女性だけ。そして私たちの嗜好は厳しく、人間が仲間に加えられる行幸は稀にしか起こらない。――幸いだった。彼女と私がほぼ同時に眷属を得たのは。もっとも二人の女王の最初の眷属は、多くの場合同時に出現するというのが言い伝えだったけれども。
私たちは幸せ者なのだと私は思った。こんなにもお互いを大切に思いながら儀式を行えるのだから。その事を彼女に言うと、彼女は笑って同意してくれた。
「立会いは?」
しきたりでは私たちが決めて良い事になっている。私の言葉は単なる確認だった。美しい私の片割れは微笑んだ。
「私は誰も――私たちの眷属にも、その場に居て欲しくは無いの」
「そうね。居るのは私と貴女と」
「そう。私と貴女と二人だけ」
恋する者に囁くように、甘い声で彼女は言った。彼女に対する愛おしさが胸を突き上げる。私たち種族の婚礼にも似た儀式。私たちは一つになり、そして繁殖の刻限(とき)を迎える。私たちは共に生まれ、そして共に還るのだろう。
私たちは聖なる森の道を辿り、一族の大いなる樹の下に行き、佳き日を占った。途中、誰にも行き会わず、私たちに双方にとってそれは吉兆だった。
3日後とそれは出た。私たちは微笑み合い、その日の準備に別れた。
「寂しい気がするわ。貴女に会える、それまでが待ち遠しい」
「すぐよ」と私は囁いた。
「きっと、すぐ」
私が帰ると私の眷属が私を出迎えてくれた。柔らかな金の髪、いつもは漂然としたその微笑みも今日はくすんでいる。
「心配しないで」と私は言った。
どんな結果になろうとも。これは私たちの定め。貴方はそれを知っているはず。
「私の女王」
私の騎士はそう言ってしばらく私を掻き抱いてから、いつ、と尋ねた。きっと彼女も今頃こうして彼女の騎士に応えていよう。3日後に。立ち会いはいらない、と。眷属の立ち会いを拒む事は稀だとも聞くけれど、定めの時に於いて、私たちは私たちの姿を誰の目にも触れさせたく無かった。
人間から産まれ出でた者にとっては残酷なのかもしれないが、残酷さを乗り越えてこそ、誇り高き女王の眷属。私は彼女の黒髪の騎士を思い起こした。彼女と同じ黒い髪。青の瞳は浮かぶ光こそ違えど、私の眷属を思わせる。私の愛する者は何故だかいつでも青い瞳を持っていた。
私たちは3日を共に過ごし、来たるべき試練にそなえて体を整えた。2日目の夜、明日に備えて早く休み、翌朝早くに私は一人で発った。私の眷属の瞳に映る表情を、私は見たくなかったから。大いなる樹に歩み寄ると私は瞼を伏せて、彼女の気配を待ち受けた。思ったとおり、予定の時刻よりも大分早く、私の片割れは慎ましい足取りで私の処へやってきた。
「私たちの霊の間にいつも平安がありますように」
私が挨拶すると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。一瞬だけお互いに抱擁しあうと、目を見交わして微笑み合う。
「それでは始めましょう」
私たちは互いに細い剣のような刃物を取り出して自分の手を傷つけた。それから細心の注意を払ってお互いの血を滴らせる。私たちの血は交じり合い、一つの大きな結晶となった。それは大きくて美しい結晶体だった。光を反射して半透明に深紅を輝かせる。私たちの命の証。互いの深い愛情。私はどんなにか、この片割れを愛したことか。
しきたりどおり、私たちはその紅石を大いなる樹の根元に埋めると、互いに向かい合った。わずかに血に染まっているお互いの剣。手の平を傷つけて、さらに血を纏わせる。私の滅び、彼女の滅び。彼女の血は私にとって致命傷。私の血が彼女に対するのと同じように。私は自分自身がひどく興奮し、同時に楽しんでいるのを知った。彼女を斃すのも、彼女に斃されるのも私たちにとっては同じこと。あの切っ先が私の身体を貫くのも、この切っ先が彼女の身体を貫くのも。
彼女の微笑で私は自分も微笑んでいるのを悟った。彼女が剣を掲げ空を切ると、剣が空気を揺るがす音が聞こえてくる。諸刃の剣は鋭く繊細で、彼女自身のようだった。その姿はきっぱりと容赦なく、鋼で出来た彫像を思わせる。飛ぶように彼女がこちらへ向かってくる様を、私は他人事のように見つめていた。金属が擦れる音がして、二つの剣が激突した。お互いの力が拮抗している事はよくわかっている。私たちは同時に飛び退り、再び仕切りなおして剣を構えた。次に切りつけてきたのもまた彼女だった。私が受け流すと、強い衝撃が両腕に走る。その痛みを無視して、私も一撃を振るった。今度は彼女がそれをかわす。互いの小さな癖も、思考さえも良く分かり合っている私たちにとって、この闘いそのものが親密な会話であり、最後の抱擁でもあった。荒ぶる力に突き動かされ、私たちは刃を交わし合った。猛々しい微笑が彼女の貌を彩ると、私の顔にもその彩が映る。私の、美しい、青い瞳の、姉妹。
幾たび斬り結んだか、もう分からなくなってしまった頃、気がつくと勝負はついていた。私のこの手の中の剣が彼女の身体に深く埋め込まれ、信じられない思いに見開かれた彼女の瞳が私を見ている。彼女の剣は私の身体を掠め、そのまま宙にとどまっていた。喜びは無かった。悲しみも。ただ、ああそうなのだという思いだけが胸に迫ってきた。
「彼に優しくしてあげて。いつくしんであげて。貴女の騎士と同様に」
胸元を石化の色に染めながら、私の片割れが囁いた。
「わかっているわ。私の貴女」
彼は貴女の眷属なのだから。貴女を愛するようにきっと愛する。なぜなら彼の中には貴女の血が溶け込み、私はきっと貴女をより感じるようになるのだから。
「怖がらないで・・・・」
こんな時なのに、彼女は私に向かっていたわりの言葉をかけた。彼女自身の血が彼女の口元から滴り落ちる。その美しい結晶を、私は唇で受け、喉で啜った。私の血は彼女への毒。彼女の血は私への毒。ただこの交わりの中で、その結晶が彼女自身ともなり、やさしく私の身体の中で溶けていく。お互いの永生をすり減らし、深い魂の交わりともなり、私の中に彼女が溶ける。身体が火のように熱くなった。ついで、目が。左目が炎のように燃え上がる。身体を二つに折って私はその痛みに耐えた。この私の剣に貫かれた彼女の苦痛を思い起こせば耐えられないわけはない。そう思うと彼女の痛みが自分の身体に重なり合った。彼女の下肢が崩れ落ちるその音を私は聞いていた。
硝子のように高価な壊れ物。私の姉妹。私の愛。私の命。最後のその時まで、彼女は微笑を湛えていた。結晶化が進み、その手が、指が、髪の先端までもが硬化して、見る間に彼女は美しい彫像となっていく。
「さようなら。私の愛しい姉妹。私の半身・・・・」
硬化した彼女の身体は脆くなり、風の振動で、自らの重さで、容易に崩れていった。私は砕け散った彼女の最後の欠片を一瞥した。これは彼女ではない。彼女の残骸、抜け殻でしかないのだ。私は自分の胸を押さえた。取り込んだ彼女の血が私の身体の中で音を立てている。少量の血は私の生命を脅かさず、だが私の生命の意味を変えていく。私の中に彼女がいた。
私は彼女の壊れた腕から落ちた剣を引き抜くと、ぎこちなく大いなる樹の根本に近寄った。二つの剣を並べて立てかけ、疲れ切った身体を物憂げにその隣に横たえる。からからと風が彼女の声を運んできた。
(怖がらないで・・・・)
私たちの霊の間にはいつも大いなる平安が横たわっている。彼女と私の間。私と彼女の眷属の間。そして私と私の眷属の間。私たちは不死の一族。永遠回帰の掟を持つ者。家路を辿り、私は私の姉妹の血と結ばれ、そして子を生す。きっとその子らは美しい子供となろう。彼女のように。私は彼女を愛するように、自分自身を愛するように、その子たちを愛するだろう。そして私の眷属もまた。
まだ生じてもいない生命を思って、私は自分の胎にそっと手を置いた。こうしてまた白夜の元に、大いなる生命の循環が廻ってくるのだ。
だが今はただ休みたかった。何も考えず、何も語らず。きっと目覚めれば、私の身体は子を産むように変化している。彼女の血を受けて変化したこの左目のように。
(私たちの平和を・・・)
彼女の声が聞こえる。私は微笑んで、そして目を瞑った。
Fin
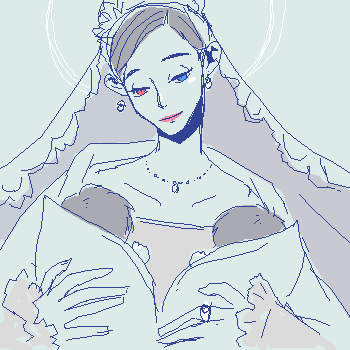
どうしようと思いつつ。
思わぬ時に萌えの火種を拾ってしまいました。秘かにファンで、いつもこそっとお邪魔させていただいておりましたCHIAROSCURO(2009.03閉鎖されました)のスズキ様のお宅の絵版で。小夜とディーヴァの「母上」の絵を見た時から。その赤と青の瞳の色を見た時から妄想が止まらなくなってしまって、遅筆、寡作、萌要素無しの3拍子揃った私が一気に書き出してしまったSSです。2次作品というよりもBLOOD+の設定をほんの少しいただいた、ほとんどオリジナルになってしまいました。
私的にはBLOOD+って、SF要素の強い作品だと思ってますので、これはしっかりSFとして書かせていただいております。スズキさんのお宅へのお捧げものです。
書いていて楽しかった・・・。今回、スズキさんのご厚意によってタイトル画および私が萌えをいただいたPBBSの絵を使わせていただきました。スズキ様ありがとうございます~~。
Back